★★★★★(*´ω`*)
著者の山本太郎さんは小沢一郎と組んだあの人ではなく、アフリカやハイチなどで感染症対策に従事した経験を持つ医師です。
「感染症」をキーワードとして読み解く人類史
狩猟生活から農耕生活に人類が移行したため、単位面積当たりの人口が増大し、感染症にとって繁栄することのできる土壌が生まれた――などなど、感染症をマクロな視点で捉え、淘汰圧や自然選択、感染力の強弱・免疫の有無などの分かりやすい要素を道具として、人類史の出来事を考察していく書物です。新書ということで200Pしかありませんが、よくまとまっています。著者の教養の豊富さとそれに裏打ちされた思索の深さには驚かされます。厭らしいところが微塵もありません。
感染症と「共生」!?
前半は、交易や戦争など人間の移動と共に、感染症も移動してスペイン風邪やペストなどの歴史上の大事件を引き起こした実例がいくつも書かれています。前半もとても興味深いのですが、私がこの本で衝撃を受けたのは後半、特に感染症を長い時間軸を使ってその「適応」の段階を紐解いていく終章です。
感染症は大抵の場合動物からやってきます。そして人間に感染するような株が現れ、小集団内の流行で終息する段階から、定期的に大流行を引き起こす段階へと人類に「適応」していきます。こうして適応した感染症は人間の中でしか生きられなくなる段階が来ます。
ところが人間社会というものは変化します。しかも変化のスピードが大きい。すると、人類に「過剰適応」してしまった感染症は、変化についていけず死滅するというのが著者の仮説です。著者は成人T細胞白血病ウイルスを実例として挙げ、徐々にこの世から姿を消していく様子を描いています。そしてこのウイルスの消滅について著者は警告を発するのです。
一方で、最終段階まで適応を果したウイルスの消滅は、別の問題を生み出す可能性がある。ウイルスが消滅した後の生態学的地位を埋めるために、新たなウイルスが出現する可能性である。
同様に、人類による感染症の根絶も著者は「過剰適応」だとみなしています。たとえ話として、洪水を防ぐためのミシシッピ川の嵩上げについて次のように述べています。
歴史家であるウイリアム・マクニールは、「大惨事(カタストロフ)の保全」ということを述べている。人類の皮肉な努力としてマクニールは、アメリカ陸軍工兵団が挑んだミシシッピ川制圧の歴史を挙げる。ミシシッピ川は春になると氾濫し流域は洪水に襲われた。1930年代に入り、アメリカ陸軍工兵団は堤防を築き始め、ミシシッピ川の封じ込めに乗り出した。おかげで毎年の洪水は止んだ。しかし川底には年々、沈泥が蓄積し、堤防もそれにあわせて高くなっていった。堤防の嵩上げは続いている。しかし、この川が地上100メートルを流れることにはならない。いずれ破綻をきたす。そのとき、堤防建設以前に彼の地を襲っていた例年の洪水など及びもつかないような、途方もない被害が起こる可能性があるというのである。
そこで著者は感染症との「共生」を唱えるのです。。
著者は感染症対策のエキスパートでもあるのですが、この文章からは、感染症を根絶するべき「敵」としてではなく、対話可能な「相手」としてとらえていることが読み取れます。初めてみる視点です。私はこれに衝撃を受けました。また、感染症の栄枯盛衰の理論をこれだけ明快に見せつけられると、なんだか切なくなってきます。人類の敵であるはずの小さな小さなウイルスに対してそんな感情が生まれたということも衝撃的です。
総評
新書とは思えないクオリティです。本では3冊目の★★★★★+評価を付けました。ぜひ読んでみてください。
参考書籍
1冊読むと関連本を10冊は読みたくなりますよね。こうしてネットワークが作られていき、泥沼にはまるわけです。
まず生物学基礎を全然知らないのでこれから。高い。
こういうのでもいいかな。

カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第1巻 細胞生物学 (ブルーバックス)
- 作者: クレイグ・H・ヘラー,ゴードン・H・オーリアンズ,デイヴィッド・M・ヒリス,デイヴィッド・サダヴァ,浅井将,石崎泰樹,丸山敬
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 2010/02/19
- メディア: 新書
- 購入: 11人 クリック: 326回
- この商品を含むブログ (29件) を見る
コンパクトにするならこれか。

- 作者: ウィリアム・H.マクニール,増田義郎,佐々木昭夫
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2008/01/25
- メディア: 平装-文?
- 購入: 37人 クリック: 1,062回
- この商品を含むブログ (85件) を見る
マクニール先生のいずれ読まなければいけないと思っている本。

- 作者: ウィリアム・H.マクニール,William H. McNeill,佐々木昭夫
- 出版社/メーカー: 中央公論新社
- 発売日: 2007/12
- メディア: 文庫
- 購入: 4人 クリック: 66回
- この商品を含むブログ (30件) を見る
本書で紹介のあった本。

文庫 銃・病原菌・鉄 (上) 1万3000年にわたる人類史の謎 (草思社文庫)
- 作者: ジャレド・ダイアモンド,倉骨彰
- 出版社/メーカー: 草思社
- 発売日: 2012/02/02
- メディア: 文庫
- 購入: 27人 クリック: 421回
- この商品を含むブログ (178件) を見る
これも本書で言及があった。少し前のベストセラー。
山本さんの最新翻訳本。欲しい。
同翻訳本。















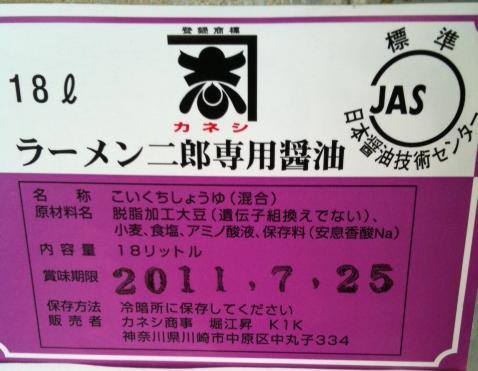






 こいつです。、、カンカン、、カン、カン、カン(1文字につき16分音符1つ)というリズムが特徴的ですよね。
こいつです。、、カンカン、、カン、カン、カン(1文字につき16分音符1つ)というリズムが特徴的ですよね。



