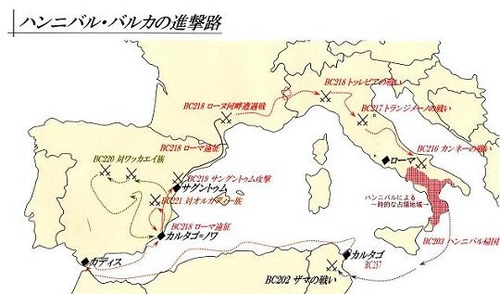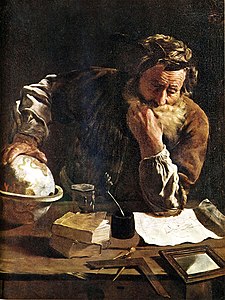★★★★★
2巻は染色体分裂~メンデル遺伝学~DNA~ウイルス遺伝学~生物の遺伝学がテーマです。1巻と同様豊富な図表が理解を強力に助けてくれることと、今回は化学知識も不要で誰でもバリバリ読み進めることができる素晴らしい本です。
DNAやばすぎ
DNAや遺伝子と言えばすっかり比喩として使い古された感があります。威張ってる好調が「我が校のDNA」なんて言いますよね。でも本書を読むと軽々しくDNAなんて言えなくなります。
DNAは私たちの体を構成する全タンパク質の鋳型です。DNAからRNAがサブセットとして抜き出され、リボソームで解釈されて細胞を構成するタンパク質ができます。
2行で書ける内容ですが、この間にはもう涙なくては読めないほどの超精巧な作業、順番が完璧に整った化学反応、適材適所の酵素の配置、エラー訂正機構、正と負のフィードバックによる濃度調節、などなど万馬券を1万回連続で当てるよりずっと難しい特大奇跡の積み重ねによって我々が生きていることを認識させてくれます。15年くらい前に流行った泣きギャルゲーとかセカチューとかコブクロとか何それちっちゃすぎ!って思えるくらいの奇跡です。生物学者はみんな宗教がかってもおかしくないです。本書ではその詳細を400P以上使って解説するのですすごい。
全体的に抱いた印象は以上ですので残りは特に気になったところを紹介します。
わたしたちの中の遺伝子組み換え
減数分裂という細胞分裂があります。ふつうの体細胞分裂は染色体が2倍になって細胞分裂し、1倍の細胞が2つできます。ところが精子と卵子は2倍になりません。染色体は半数になります(正確には2倍になってから1/4になります)。半数と半数の染色体が結び付いて一人前の受精卵ができるというわけです。子供は精子と卵子の遺伝子をランダムで受け継ぐため多様性が生まれます。
ところがたまげたことがあって、減数分裂時も組換えがあるそうなのです。分裂前に染色体同士が交差して、そのまま入れ替わってしまうらしいです!乗り換えと呼ばれています。

特定健診(メタボ)対策・ダイエット レシピ集|生活習慣病予防の総合健康情報サイト|メタボヘルプ ドットコム【遺伝子ふしぎ発見!】
つまり我々のキンタマの中では毎日遺伝子組み換えが起こっているというわけですよ!びっくり!これは有性生殖に加えてもう一段階進んだ遺伝的多様性を生み出します。精子や卵子全員に遺伝的な個性があるだなんて知りませんでしたよ。
宇宙人バクテリオファージ
これは高校生物でも習うので知っている人も多いと思います。私は習ったような気がしますが忘れました。
ウイルスとは自己増殖だけを目的としたDNAとそれを囲むタンパク質だけでできた存在です。自分で栄養を合成したりできないので、生物とはみなされません。他の生物に寄生することだけが彼らの生きる道です。
で、このウイルスの例として挙げられているT4バクテリオファージが怖いのです。

なんですかこの宇宙人!
ウィルス『ファージ』がまるで人工物のようだと話題に。 – NAVER まとめ

細胞を刺してDNAを注入するファージ
ウィルス『ファージ』がまるで人工物のようだと話題に。 – NAVER まとめ

ファージに取りつかれた細胞は破裂して死ぬ
高等学校生物 生物I‐遺伝 – Wikibooks
DNAを注入された細胞はお人よしなことに細胞内器官が「わーいDNAが来たよー合成合成」とウイルスのDNAを使って、しかも自分のエネルギーを使ってウイルスのタンパク質を合成してしまい、上図のようなことが起きます。しかもウイルスなんて単純ですから大量に合成してしまいます。増殖したウイルスは細胞壁を溶かす酵素を出して細胞を壊し大量のウイルスが飛散、被害が拡大していきます。おそろしい
また、ウイルス由来のDNAは宿主細胞のDNAを組み替えてしまいます。そして宿主のDNA内で長い間潜伏し、例えば宿主の体調が良くなった時など(細胞内の特定の物質の濃度でわかるそうです)を狙って発現し増殖します。トロイの木馬ウイルスみたいなもんです。コンピューターで発明される前に、生物プログラムとして存在していたとは。見た目の怖さも抜群ですがここは心底ゾッとしました。
インフルエンザにかかったあなたはこれが体内で起きています。
ところがこいつを病原菌にとりつくように改造(というか抽出と培養)すれば、病原菌だけを安全に殺すことができます。これを使って最近流行の多剤耐性菌を退治することも期待されています。ファージセラピー です。宇宙人も使いよう。
他にも遺伝的多様性に貢献したり病気の原因になったりするきまぐれなトランスポゾンとか細胞内のちょっとした物質の増加でスイッチの入るアポトーシス(細胞死)の仕組み怖いとか近親婚に病気が多い理由(劣性遺伝子がかち合いやすいから)とかDNA複製の心細すぎる仕組みとか驚愕した例はいっぱいあるのですが、時間と紙面の関係でここまでにします。気になる方はぜひ読んでみてください!
シリーズの4枚目です。

























![Vespro Della Beata Vergine [DVD] [Import] Vespro Della Beata Vergine [DVD] [Import]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51%2Bf3ebRFNL._SL160_.jpg)