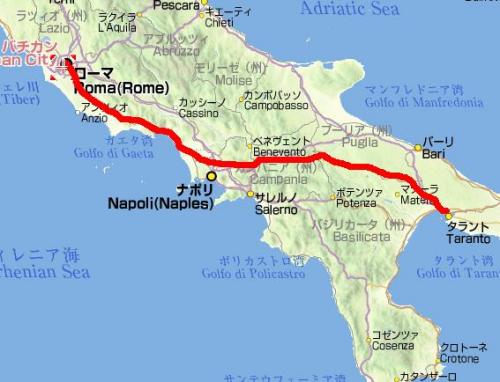今週もレポートは少なめでした。
3435サンコーテクノ

壁面に器具を固定するアンカーというとても地味な業界の日本トップ企業です。主力製品は「あと施工アンカー」という、コンクリートが固まった後に取り付ける器具で、これだけで全売上の3/4を占めます。アンカーや取り付け工具の製造・販売はファスニング事業と呼ばれており、営業利益率は8~10%と高めです。
あと施工アンカーのサンコーテクノ株式会社|ファスニング営業本部
このページが面白いですね。
あと施工アンカーのサンコーテクノ| こんなところにサンコーテクノ
同社の営業成績は建築需要と連動します。したがって不景気の時は絶不調になります。しかし過去の実績のグラフを見ると最悪のリーマンショック期でも赤字には至らなかったようです。底堅い製品です。

また同社の強みは、新築マンションだけではなく、中古マンションのリニューアルや、高速道路・自動販売機・ガソリンタンク・ソーラーパネルなど、固定が必要なあらゆる場所に需要があることです。これらはどれだけ不況であろうとも全くなくなることは決してありません。近年の目覚ましい利益率の上昇にも驚かされます。
肝心の株価は、直近の8/11発表で営業利益-35.8%というクソ1Q決算を発表したため、なんと2割以上も下がっています。

波があって不安定なチャートですね。面白い企業ですが手を付けるのは憚ります。
2928 健康コーポレーション

ある意味日本で最もホットな銘柄ですね。メイン事業は誰もが知ってるライザップ。1Qにライザップの広告を大量投入する同社は先日の1Q決算でまさかの営業黒字を達成し、通期決算への大きな期待が生まれました。同時に海外展開やら医療データ活用サービスへの進出やらビッグなIRを打ち出し、期待感を煽ります。

中期計画はネジが吹っ飛んでいます。

イメージ通りのお笑い銘柄ですね。
14年→15年の230億→390億という実績も凄まじいですが6年後に3000億って頭おかしいんでは!?利益率も2倍以上になってるし、、ここまでやるには、アップルのように放っておいてもユーザーが物凄い勢いで増加し、しかも高い製品を買ってくれるという新興宗教のようなブランド力を構築しなければなりません。次の本を読んで私はアップルを新興宗教と判断しました。私は同社にこれの真似をすることはできないと思います。
投資家の目は現実的でした。株価はいまいちな動きをしています。

5月末をピークに全くぱっとしませんね。決算発表後も700→610と奮いません。先週の株安の流れを引き継げばピーク時の半額になりそうな勢いです。5月末が熱狂し過ぎていただけなのかもしれませんが。
3186 ネクステージ(やや良)
 b
b
名古屋が本拠地の中古車販売業者です。典型的な店舗数拡大の成長モデルですが、近年店舗数を大幅に増やしたことで、売上高が急成長しています。

同社の急成長の理由はオートオークション市場からの中古車の調達が可能になったことです。中古車業界は一般的に自分の縄張り内で車の売買をするため、商圏が限られ多店舗展開をすることがなかなかできませんでした。しかし同社は他社に先駆けて全国展開し、名古屋の企業ながら関東圏にも中京圏と同数の店舗を展開しています。ここ3年で店舗数は2.3倍になりました。
今期は店舗数を48→60に急増させる予定です。同社は低価格を売りにしており、市場競争力が強く他店を圧倒する力があります。このまま順調に店舗数を増やしていけば、高成長はほぼ間違いありません。
一方弱みもあります。中古車業界共通の悩み、消費増税です。14年度決算は売上が急増しているにもかかわらず純利益が13年度の半分になっています。増税があれば競争力うんぬんよりまず需要が無くなります。1年半後の消費増税時には、大幅な業績低迷が運命づけられているようなものです。逆にそこをうまく乗り切れば、安泰といえるのですが、、

株価はうねりまくりながら近年大きく上昇しています。7月に投機的に2倍近くに急上昇した後下がり、直近でも金曜日に-7.32%も下げてPER9.11倍となっていますので、明日激しく下がれば買い時かもしれません。
2412 ベネフィット・ワン(面白い)
福利厚生サービスのアウトソーシングを行うというとても面白いビジネスモデルの会社です。企業が同社に入会金と月会費を払い、同社は企業に向けて従業員向けのサービスを提供するというモデルです。例えば、
・英会話スクールの割引
・研修に使う国内・海外施設の割引利用
・ベビーシッター・託児施設の割引利用
・分譲住宅の割引(!)
・心の悩み・育児・介護相談
などなど。分かりやすい図が有報にありました。

クライアントには官公庁もいます。会員数はすでに700万人以上と巨大です。割引サービスはあまり金がかからないからなのか、利益率は15.5%と非常に高い優秀企業です。中期計画では会員数1000万人を目指し、成長規模を拡大させるために更なる多角的な展開をする予定です。
上で説明した福利厚生事業は売上高の約半分を占める中心事業ですが、最近伸びが著しいのはパーソナル事業です。これは福利厚生事業の個人版です。個人から会費を徴収し割引サービスを提供するというものです。すでに同社の売上の1割以上を数え、伸び率も前期+90%超と有望な事業です。そのサイトは
とく放題
ここです。ソフトバンクと提携し、月会費500円を払うとラクーア734円割引だのマック・ケンタッキーの割引だの抽選でコンビニの商品プレゼントだのさまざまな割引サービスが受けられます。スマホと連携しているので流行りそうです。
他にも多数新規事業を用意していて前途有望ですが、残念ながら株価が高すぎました。

1年で3倍という偉業を成し遂げていますがそれから1/4ほど下げ、未だにPER32.18倍です。明らかに急成長株の上がり方ですから、今後業績が加速しない限り大幅な伸びは期待できないでしょう。2000円台を割り込んだらちょっと興味が出そうですが、金曜日に余り下げていないことを考えるとたぶんありえません。
おわりに
さて、世の中には面白い企業がたくさんあることをフィスコのレポートと企業のウェブサイトからたくさん教えていただきました。感謝しています。
この試みはしばらく続けるつもりですが、フィスコは同じ銘柄を3か月ごとにレポートし続けることが多く、以前と同じ企業のレポートが続出してきました。以後、取り上げられる銘柄の数が減りそうです。
直近、金曜のえげつない下げと、明日予想される暴落で年初来成績がマイナスになる恐れがあり泣きそうですが、それとはまた別の理由で、株の記事の趣向を変えるつもりです。
私の投資スタンスは中長期なので、短期的に株価動向を書いたりする記事はもう書かないつもりです。というのも、テクニカルな数字の大小を細かく議論するのって、正直言ってつまらないのです。それよりも、いろんな企業がいろんなことを考えていろんなビジネスをしている、その事実を追っかけるのが楽しくて仕方ありません。
以前Core30の銘柄調査をしていましたが、時間が無くなっていったん打ち切りました。大体7割くらいの企業のウェブサイトをざーっと見ました。これはとても面白い経験でした。日本を支配している企業がどのようなものか知り、ビジネスの動向や日本経済の仕組みを極めて分かりやすくしかも実践的に把握することができます。
これをもう一度、TOPIX100でやってみようかな、と思いました。以前やっていたよりもう少し時間をかけて、1企業に関するレポートを作るのです。たぶん1年以上かかるので、その間に日本経済の動向も少々変わってしまうかもしれません。銘柄の入れ替えも行われるでしょう。でも企業のサイトって面白いんですよ。インターネットが発展し、企業がIRで情報を公開しなければいけなくなったことは、すばらしいことです。私たちが生きていく上でモノやサービスを購入する時、その裏で企業がどんなことを考え、どんな風に社会や人間を捉えて行動しているかを知ることができるのです。親切にも彼らはその仕組みを、すなわち意識から無意識に至るまで消費者に金を払わせるための動機づけのために彼らがしていることを、(都合のいいことだけとはいえ)オープンにしてくれているのです。これを利用しない手はありません。
前回は番号が小さい順だったので、今度は大きい順に。まずは9984ソフトバンクです。他にもやることが多く一体いつになるか分かりませんが、地道に調べていきます。










 b
b